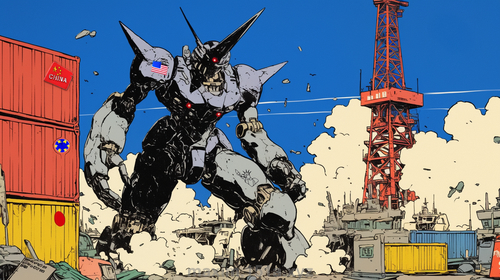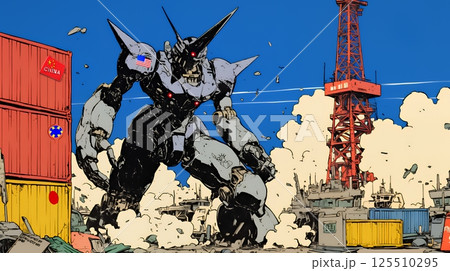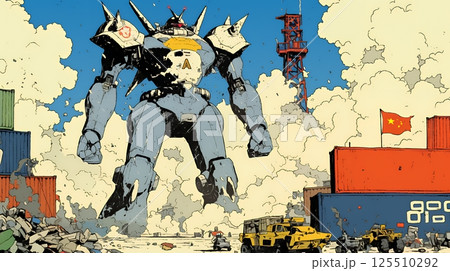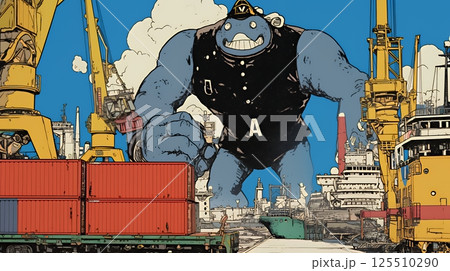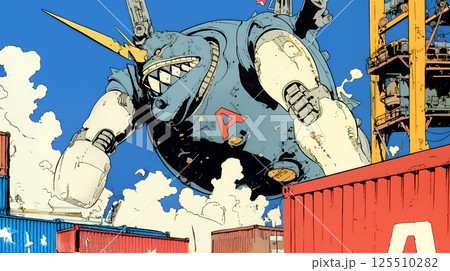風が吹けば桶屋が儲かる
# かぜがふけばおけやがもうかる
か
風が吹けば桶屋が儲かる
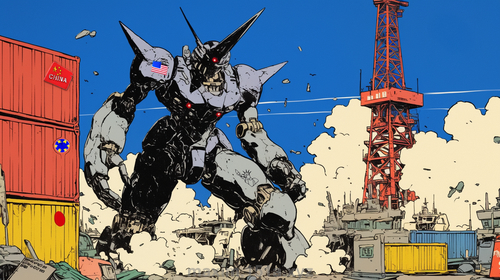
種類:その他格言
風が吹けば桶屋が儲かる
『風が吹けば桶屋が儲かる』ということわざは、一見無関係に思える事象が連鎖的に結びつく様子を表しています。昨今の米国大統領の行動も、常人には計り知れない連鎖的な政策意図が隠されているのかもしれませんね。
広告
トランプ大統領の関税政策とその影響
風が吹けば桶屋が儲かるか、それとも急いては事を仕損じるか
アメリカのトランプ大統領が推し進める一連の関税政策は、「アメリカ第一主義」の名のもと、国内産業保護を目的として展開されています。しかし、その実態は、経済の複雑な相互依存関係を無視した場当たり的な対応であり、自己中心的なパフォーマンスに過ぎないのではないでしょうか。
歴史を振り返ると、ある事象が予期せぬ形で他の分野に波及し、大きな変化をもたらすことは珍しくありません。たとえば、インターネットという「風」が吹いたことで、オンラインショッピング市場が拡大し、物流業界や倉庫業界が潤ったように、「風が吹けば桶屋が儲かる」こともあります。しかし、インターネットの発展は自然発生的な技術革新によるものであり、そこには社会全体の最適化という視点がありました。
対して、現在進行形のトランプ氏の関税政策はどうでしょうか。それは、経済の生態系に強引に風を吹かせ、自分に都合の良い桶屋だけを潤わせようとする、不自然で偏った試みに見えます。しかも、その“風”は他国との摩擦を激化させ、報復関税という形で米国内の消費者、農業、製造業に跳ね返っています。もはや「風が吹けば桶屋が儲かる」という悠長な話ではなく、「風が吹けば隣家の窓ガラスが割れる」と言った方が実態に近いのかもしれません。
このような自己都合の政策運営がもたらした混乱は、まさに「急いては事を仕損じる」の典型です。1930年代のスムート・ホーリー関税法が世界恐慌を悪化させた歴史から何も学ばず、同じ過ちを繰り返す姿勢には、国家運営における慎重さも、歴史的教訓への敬意も見られません。
国家のリーダーが、自らの支持層へのアピールを最優先し、短期的な人気取りのための経済政策を振りかざし続けるとき、犠牲となるのは国民の生活であり、国際的な信頼関係であり、次世代の可能性です。関税という「風」は、確かに一部の「桶屋」を一時的に潤しているかもしれません。しかし、その影で、多くの無関係な人々が土ぼこりに目をやられ、行き場を失っていることを忘れてはなりません。
とはいえ、すべてが失敗に終わるわけではないのも歴史の皮肉です。混乱のなかから、結果として新たな連携や産業構造の見直しが進み、思いがけない場所で未来の「桶屋」が芽吹くこともあります。たとえば、過剰な中国依存から脱却し、サプライチェーンの多様化が進んでいるのも、副次的な影響のひとつでしょう。
だからこそ、私たちは政策の是非を問い続けると同時に、予期せぬ変化にも目を凝らす必要があります。
歴史に学び、未来に備える。その過程で、想像もしなかった風が、思いがけず誰かを潤す――そのような可能性すら含まれているのです。
風が吹けば桶屋が儲かる
このロボットの行動が、未来の世界の発展につながることを願うばかりです。
当初は、下の絵のように「風が吹けば桶屋が儲かる」の英語訳である「バタフライ効果(butterfly effect)」をテーマに作画していましたが、急遽差し替えることになりました。